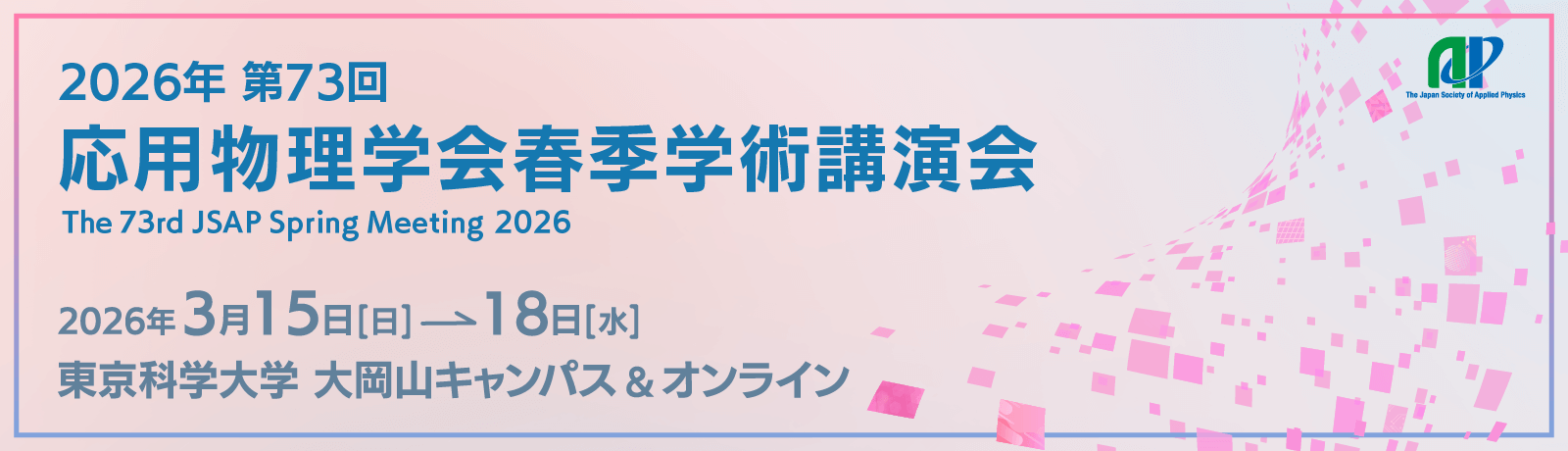チュートリアル
開催方法
- 講演は現地+オンライン(Zoom)のハイブリッド開催です。
- お申込み締切は、2月27日(金)正午です。当日受付はございません。
- ウェブ会議室URL及び講義資料(PDF)は、3月5日(木)にメールにてご案内する予定です。講義資料の紙による配布はございません。
- 当チュートリアルは録画し、講演会終了後、3月27日(金)~4月9日(木)の間、チュートリアル参加者限定の見逃し配信を実施予定です。
- チュートリアルのみ参加される場合は、春季学術講演会の参加申込は必要ありません。
チュートリアル一覧
- 半導体製造における低温プラズマプロセスの基礎と応用 林 久貴(ダイキン工業株式会社)
- 新スピントロニクス入門―スピン流から最新の基礎・応用まで― 鈴木 義茂(情通機構研究員、産総研招聘研究員、大阪大学招聘教授、大阪工業大学客員教授)
- 二次元材料トランジスタの基礎技術 長汐 晃輔(東京大学)
- インフォマティクス応用入門Ⅲ 実践編 高原 渉((株)日立製作所/奈良先端大)
講義内容
| 題目 | 半導体製造における低温プラズマプロセスの基礎と応用 |
|---|---|
| 日時/会場 | 3月15日(日) 14:30~17:00 M-103会場 |
| 大分類 | 8.プラズマエレクトロニクス |
| 内容 | 講義内容:半導体産業における微細加工の高度化に伴い、低温プラズマプロセスはナノスケールでの高精度加工を可能にする不可欠な技術として広く利用されています。特にプラズマエッチングは、高アスペクト比構造や複雑なパターン形成を実現し、ロジック、メモリ、パワーデバイスなど幅広い分野で重要な役割を果たしています。また、材料選択性や表面改質に優れ、次世代半導体技術(3D構造、先端パッケージング)においても中心的な技術です。 本チュートリアルでは、主にエッチング用途で使用されるプラズマ装置の構造と動作原理、代表的なエッチング事例、さらにプラズマ診断・解析の具体例について解説します。加えて、近年注目されている機械学習を応用したプロセス開発手法として、新規ガスの探索やエッチング条件の最適化事例を紹介します。 |
| 講師名・講師略歴 | 林 久貴(ダイキン工業株式会社)
東京大学工学部卒業後、同大学院にて修士号(1989年)、博士号(2003年)を取得。1989年より(株)東芝にてDRAM、ロジック、NAND、STT-MRAMのプロセス開発に従事。2017年から2021年にかけてキオクシア(株)で3D NANDおよびPCMプロセス開発を担当し、名古屋大学特任教授として低温エッチング技術の研究を推進。2022年よりダイキン工業(株)化学事業部にてドライエッチング用ガスの開発に従事。専門分野は半導体向けプラズマエッチング。 応用物理学会フェロー。 |
| 題目 | 新スピントロニクス入門―スピン流から最新の基礎・応用まで― |
|---|---|
| 日時/会場 | 3月15日(日) 9:30~12:00 S2-203会場 |
| 大分類 | 10. スピントロニクス・マグネティズム |
| 内容 | 概要:1980年代に始まったスピントロニクスについて歴史と単位から始めて、磁性の基礎を学んだうえでスピントロニクスの基本的な原理を理解する。そのうえで超高感度磁気センサーや固体磁気メモリなど日々進歩する応用について知ることができる。スピントロニクスには特殊な専門用語が多く近づきにくいと感じている他分野の研究者、あるいはこれから勉強する初学者向けの講義。
講義1:磁性の基礎と諸物性
参考書:「スピントロニクス」鈴木義茂他著,共立出版 |
| 講師名・講師略歴 | 鈴木 義茂(情報通信研究機構研究員、産業技術総合研究所招聘研究員、大阪大学招聘教授、大阪工業大学客員教授)
<学歴および研究経歴> 1984年 筑波大学大学院修士課程理工学研究科修了 <受賞> |
| 題目 | 二次元材料トランジスタの基礎技術 |
|---|---|
| 日時/会場 | 3月15日(日) 9:45〜12:00 M-103会場 |
| 大分類 | 17.ナノカーボン・二次元材料 |
| 内容 | MoS2に代表される2次元材料をチャネルとした3次元ナノシート構造が2022年のIEDMでTSMCにより発表されて以来、2次元材料もPMOSナノシート上にNMOSナノシートを3次元配置する「CFET」構造による集積化の研究が急速に進んでいる。本チュートリアルでは、2次元半導体の基礎物性に基づき2次元材料が次世代チャネルとして期待される理由を説明する。また、コンタクト形成、ゲートスタック技術、集積化等の基本的な考え方から世界的な動向についても紹介する。現状・課題を明確にすることで、将来展望を議論できる機会にしたい。 |
| 講師名・講師略歴 | 長汐 晃輔(東京大学)
東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 教授 2002年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了.海外特別研究員(米国スタンフォード大学),宇宙科学研究所助手,東京大学大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻講師,准教授を経て,2020年より現職. |
| 題目 | インフォマティクス応用入門Ⅲ 実践編 |
|---|---|
| 日時/会場 | 3月15日(日)9:30~12:30 S2-204会場 |
| 大分類 | 合同セッションN「インフォマティクス応用」 |
| 内容 | マテリアルズ・インフォマティクス(MI)などのインフォマティクス応用もその登場から時が経過し、黎明期から活用期に入っている。そして、インフォマティクス応用の中核をなすAI技術の進化・発展の速度は生成AIの台頭をはじめ、めざましいものがあり、インフォマティクス応用の取り組みは多様化の一途をたどっていると言って差支えないだろう。しかしながら、こうして取り組みが多様化をしている一方で、自身がインフォマティクス応用の普及促進の活動をしている中で、産業界・学術界共に、実際のモノづくりにおいてインフォマティクス応用をどうすればうまくできるのか?といった悩みの声が数多くあるように思う。 本チュートリアルでは、これまでのインフォマティクス応用入門Ⅰ、Ⅱを受けて、実際のモノづくりにおいてどのようにインフォマティクス応用をすればよいのかについて、著書「マテリアルズ・インフォマティクス実践ハンドブック」を題材として、実際のモノづくりテーマに即した内容を取り上げる。データ分析の考え方・AIフレンドリーなデータのあり方・AIプロジェクトの進め方(要件整理・タスク設計)から、各種データ(表形式・画像・テキスト・スペクトル・時系列・材料構造、など)におけるAIモデルの構築・活用及び生成AI(LLM)+RAGなどに至るまで、多様化するインフォマティクス応用の取り組みにどう向き合うかべきかを扱う。本チュートリアルを通じて、実際のモノづくりにおけるインフォマティクス応用の足がかりを掴んでもらえれば幸いである。 |
| 講師名・講師略歴 | 高原 渉((株)日立製作所/奈良先端大)
名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程修了。材料工学専攻出身からメーカーでのMIを活用した材料開発業務を経て、日立製作所入社。現在は、データサイエンティストとして日立の材料開発ソリューションに従事し、多様な民間企業のデータ分析・コンサルティング・講演・教育などを行う。また、奈良先端科学技術大学院大学にてMI領域の研究活動にも従事している。趣味はデータ分析でテーブル・画像・テキスト・材料構造など幅広いタスクのデータ分析コンペに参加し研鑽を積んでいる。Kaggleコンペティション「Vesuvius Challenge – Ink Detection」準優勝。Nishikaコンペティション「材料の物性予測」3位入賞。Kaggle Competitions Master。社外講演や執筆活動、学会活動などを通してMIの普及促進を行っている。著書「マテリアルズ・インフォマティクス実践ハンドブック」(森北出版)。2021年度日本コンピュータ化学会論文賞(吉田賞)受賞。日本コンピュータ化学会理事。有機合成化学協会「AI と有機合成化学」研究部会幹事。 |
申込方法
- 2月27日(金)正午までに、当ページ下部の申込みボタンより、申込み及びご入金を完了させてください。
- クレジットカード決済(VISA、master、JCB、American Express、ダイナースクラブ)・コンビニ決済(ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ)がご利用いただけます。
- お申込み完了後に、ご登録いただいたメールアドレス宛に領収書URLを記載したメールが自動送信されます。領収書はインボイス対応しています。他の形式をご希望の場合はmeeting(at)jsap.or.jpまでご連絡ください。
受講料(講義資料PDF含む)
| 社会人・学生(会員・非会員) | 5,000円(税込) |
オンライン視聴・現地参加方法
オンライン視聴方法
- 3月5日(木)にチュートリアル参加用URLと、講義資料(PDF)を、お申込みいただいた皆様に、メールにてご案内する予定です。こちらのメールをチュートリアル当日まで保存願います。メールが届かない場合はmeeting(at)jsap.or.jpまでご連絡ください。
- チュートリアル開始時刻になりましたら、メールに記載のリンクより、ご入室ください。
Zoomのウェブ会議システムを利用して開催します。
視聴にあたり、Zoomの有料契約を結んでいただく必要はございません。 - 講演会場には、聴講者の方がご利用できるオンライン環境はありません。オンライン参加される方は、自宅・勤務先・宿泊先等よりご参加ください。
- 受信映像の保存(画面キャプチャを含む)、録音、録画、再配布は禁止です。チュートリアル資料の再配布は禁止です。
現地参加方法
- 会場入口にて受付のものに名前をお伝えいただき入場してください。
- 当日参加申込は受け付けておりません。参加希望の方は、2月27日(金)正午までに以下よりお申込みください。
参加申込
チュートリアル参加申込「半導体製造における低温プラズマプロセスの基礎と応用」
チュートリアル参加申込「新スピントロニクス入門―スピン流から最新の基礎・応用まで―」
チュートリアル参加申込「インフォマティクス応用入門Ⅲ 実践編」
締切以降の参加申込は受け付けておりません。ご了承下さい。