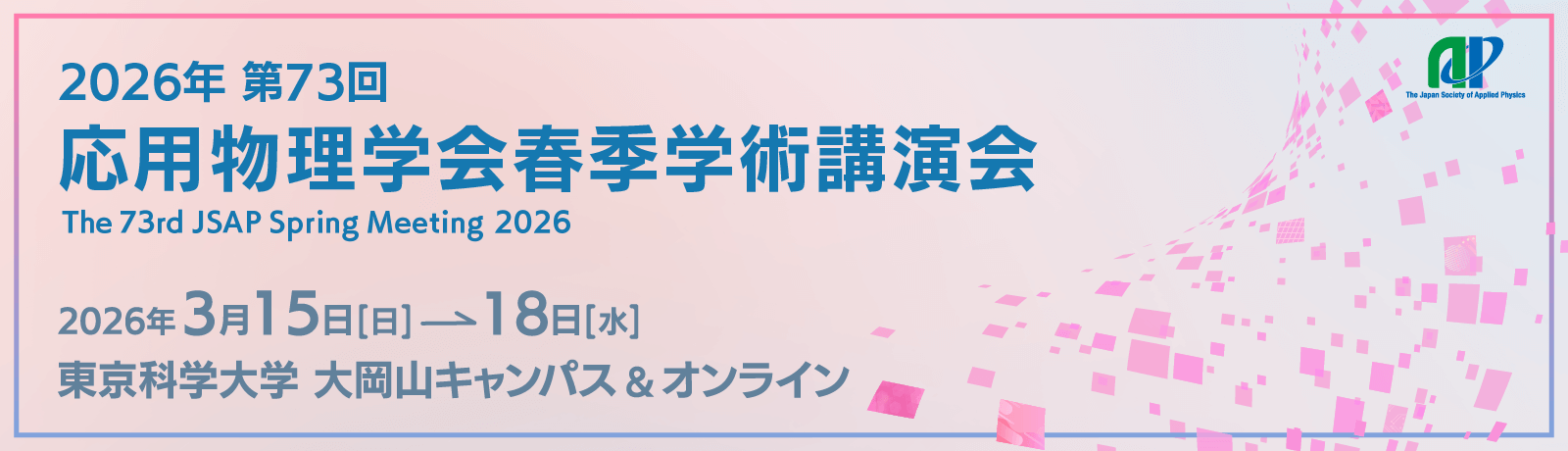注目講演
注目講演
春講演会プログラム編集委員が選んだ16件の注目講演です。
| 中分類分科名 | 講演番号 | 講演タイトル | 講演者 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目講演推薦理由 | ||||
| 2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育 | 17p-S2_201-8 | 生体マウス撮影用大面積高解像度X線カメラによるAt-211投与マウスの全身イメージング | 菊池 優花 | 早大理工 |
| At‑211は標的アイソトープ治療に適したα線放出核種として注目されており、様々な標的分子への適用によって治療対象の拡大が期待されている。臨床応用に向けては、標識体の安定性、薬物動態、安全性を評価するためのマウスモデルを用いた前臨床試験が不可欠であるが、集積を評価するためにはヒトと比べてより高い解像度が必要である。本研究は、At-211の崩壊系列中に発生する79keVのX線を利用し、1mm以下の高解像度でマウス全身の集積を可視化可能なX線カメラを開発したもので、前臨床評価の精度向上に寄与し、At-211を用いた標的アイソトープ治療の発展に貢献するものと期待される。以上の理由から、本講演を注目講演として推薦する。 | ||||
| 6.1 強誘電体薄膜 | 16a-M_278-6 | 単分子誘電体に基づくアナログ・忘却特性を併せ持つメモリへの展開 | 有馬 將稀 | 広島大院先進理工 |
| 最近見出された単分子誘電体POMの分極が「刺激で連続増大」「遮断で自然減衰」する動的応答を利用し、アナログ性と忘却性という相反要件を単一材料で両立した脳型メモリ素子をFETで実証した。これは低電力ニューロモルフィック実装へ展開が期待される。 | ||||
| 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 | 17a-M_103-11 | RAXIO®におけるRadical/Ion switchを用いたトレンチ形状制御プロセス | 瀧本 壽来生 | 日立ハイテク |
| 半導体デバイスの高集積化に伴い、三次元構造の開発が加速するとともに、高アスペクト比微細構造の精密な形状制御が喫緊の課題となっている。本発表は独自の Radical/Ion switch機能によりトレンチ側壁の保護膜厚の制御について報告する。トレンチ部の仕上がり形状を制御可能とする本技術は、今後のプロセス開発を加速させることが期待される。 | ||||
| 11.5 接合,回路作製プロセスおよびディジタル応用 | 17p-W8E_308-2 | 半磁束量子回路の論理ゲートの動作実証 | 富田 瑠伽 | 名大 |
| 磁性ジョセフソン接合であるπ接合を利用した低電力超伝導集積回路の研究開発が行われている。本講演は、π接合を含む新たな超伝導集積回路プロセスを開発し、π接合を組み込んだ回路を作製して実験的にテストした初めての報告であり、注目講演として推薦する。 | ||||
| 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 | 16a-M_124-7 | 無輻射再結合の抑制による発光可能な有機太陽電池の開発 | 伊澤 誠一郎 | 東京科学大フロンティア研 |
| 本発表では有機EL分野で用いられる多重共鳴熱活性化遅延蛍光分子を利用することで、有機薄膜太陽電池を効率的な発光素子として動作させた結果を報告する。これは有機薄膜太陽電池の課題である電圧損失を削減することや、発光・発電の双方の機能を有するマルチファンクションダイオードの実現にもつながるため、学術的・産業的にも重要であり、注目講演に推薦する。 | ||||
| 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス | 16p-M_107-1 | Photonic Crystal Surface Emitting Lasers – A Perspective of Nano-Photonics Research & Commercialization from the United Kingdom |
Hogg Richard | Aston University |
| フォトニック結晶面発光レーザーは高品質かつ超高出力なレーザー発振が可能であることから、近年、注目されているデバイスである。本講演では、この最先端光デバイス開発の取り組みを結晶成長やデバイス設計、ナノ加工の観点から紹介する。特に、英国における研究や産業化の取り組みについても紹介されることから、世界的潮流を知ることができる注目の講演といえる。 | ||||
| 15.4 III-V族窒化物結晶 | 16p-W2_401-13 | サファイア基板上AlGaN系レーザーダイオードの318 nm室温CW発振 | 三宅 倫太郎 | 名城大理工 |
| 本講演は、医療・産業分野で期待されるUV-Bレーザーの室温連続発振(CW)をサファイア基板上AlGaN薄膜で実証した画期的な報告です。低温成長による界面の急峻化や放熱構造の最適化により、波長318 nmでの動作を達成しました。実用化を大きく手繰り寄せる成果であり、注目講演に相応しい内容です。 | ||||
| 17.3 層状物質 | 17a-M_178-9 | AI agentとロボット技術を統合した高品質二次元半導体作製 | 出原 渉 | 京大エネ研 |
| 二次元層状物質の人口ヘテロ構造を、人間の経験に頼らずに、AI agentとロボット技術を組み合わせて高効率で作製することに成功した研究である。結果として、人間の手で作製したものや過去にロボットが作製したものより数倍高い単層MoS2の発光強度が得られており、現代的でインパクトも高い内容であることから、注目講演にふさわしいと判断する。 | ||||
| 21.1 合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 | 17p-W9_324-7 | EFG法による150 mm β-Ga2O3 (001)単結晶の育成 | 長谷川 将 | NCT |
| 100 mmサイズのβ-Ga2O3 (001)基板を用い,高耐圧・大電流酸化ガリウムデバイスが実証されている。本講演では,EFG法による150 mm (001)バルク単結晶育成技術を構築し,150 mmサイズの基板の製作に成功した成果が報告される。大口径化により,酸化ガリウムパワーデバイス本格量産への展開が期待され,学術・産業双方の観点から極めて重要な成果と言えるため注目講演として推薦します。 | ||||
| 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」 | 18p-S2_204-1 | 物理情報に基づく取得関数の重み付けによる酸化物薄膜成長のベイズ最適化 | 若林 勇希 | NTT 物性研 |
| 情報科学技術の活用が様々な分野で進んでいるが、データから有用な法則を取得するデータ駆動に加えて既知の知識の活用により、より合理的なモデル化・解析・意思決定を行う試みが注目されている。本講演はベイズ最適化(BO)に結晶成長の事前知識を導入する physics-informed BOを提案し、 LaAlO3のMBE成長へ適用し、探索を有望条件領域に誘導することで、少数の実験で良好な結果を得た。 | ||||
| FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」 | 15p-M_123-1 | カオス的量子拡散モデルによる量子データ分布の学習 | チャン クオック ホアン | 富士通 |
| カオス的ハミルトニアン時間発展を用いた新しい量子拡散モデルにより量子データ生成する新たな手法の提案。既存手法が要求する量子ビット個別の精密操作、時間依存の複雑な制御を要さないため、ハードウェア適合性と頑健性を向上させる技術である。量子データ生成の実用化を後押しし、量子化学や材料探索等への応用にも寄与する可能性があり、注目に値する。 | ||||
| KS.1 固体量子センサ研究会 | 18p-W9_324-8 | 走査型光電流顕微鏡による単一NV中心画像の空間分解能 | 中村 駿希 | 東北大院工, 東北大 WPI-AIMR |
| ダイヤモンドNV中心は高感度量子センサとして注目され、これまで主に光学的検出が用いられてきた。本発表では、応用上重要となる電気的検出手法に着目し、単一NV中心の空間分解能について光学的検出と実験と数値計算の両面から検討した。その結果、電気的検出がより高い空間分解能を有することを明らかにした、注目に値する講演である | ||||
| T1 Lab to Fab 2:量産化とグリーン化を突破するための半導体研究 | 16p-W9_222-7 | プロセスインフォマティクスによる半導体製造技術の深化 | 髙石 将輝 | アイクリスタル |
| 高度化する半導体製造にプロセスインフォマティクスが解を示す。数理モデル×実測データで最適化し、開発から量産までを一気通貫で加速。品質・生産性、省資源・省エネを同時に実現する事例を紹介する必聴講演。 | ||||
| T13 原子層プロセス(ALP:Atomic Layer Process)の解析技術と応用技術(3) | 15a-70A_101-4 | New Paradigms in Atomic Layer Deposition for 3D Semiconductor Device Fabrication | Han-Bo-Ram Lee | Incheon National University, ACS Publications |
| ASD(Area Selective Deposition)を先端半導体デバイスの補完的パターニングとして位置づけ,阻害剤によるブロッキング向上で工程複雑性とアライメント要求を低減する指針を示す。さらに深層学習フレームワークを用いたAI駆動型材料探索を推進し,
次世代デバイス向け高誘電率誘電体など,用途特化型機能材料開発の一環を紹介する。 |
||||
| T16 ナノバイオテクノロジー分野におけるインフォマティクス技術の応用 | 15p-WL1_301-9 | ナノ・量子・AIを駆使した単一分子識別 | 谷口 正輝 | 阪大産研 |
| ナノギャップを用いたトンネル電流計測を技術基盤とする生体分子シークエンサーにAIと量子計算を融合した単一分子識別技術で、次世代ゲノム解析等を切り拓く先端的な研究です。 DNA・RNA・ペプチド配列と多様な化学修飾を1分子レベルで同時解読しうるプラットフォームとして、疾患バイオマーカー検出や高スループットゲノム医療への展開が期待されます。 | ||||
| T20 光機能材料と界面制御によるエネルギー変換研究の新展開 | 15p-M_374-2 | カルコゲナイド系化合物半導体光触媒および光電極を用いたグリーン水素生成 | 工藤 昭彦 | 東理大理 |
| カルコゲナイド系光機能半導体のバンド・界面制御を基盤に、可視光水分解・CO₂還元を犠牲試薬なしで実現するZスキーム光触媒・光電極系を創出。光吸収・電荷分離・界面反応を統合制御するエネルギー変換研究の最前線を示し、本シンポジウムの中心課題を牽引する注目講演である。 | ||||
| T24 人間 × AI × ロボティクスが拓く自律材料研究のフロンティア | 16a-70A_101-5 | 基盤モデルを活用した経験・科学知のデジタル化 | 畠山 歓 | 東大工 |
| ChatGPTに代表される「基盤モデル」を材料科学へ応用する先端研究の講演となります。単なるデータ解析にとどまらず、マルチモーダルAIやロボットを用いて、実験現場の暗黙知や経験則までデジタル化する試みに注目したい。実験プロセスの全自動化と研究DXの未来像を提示する、応用物理学会ならではの発表です。 | ||||